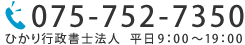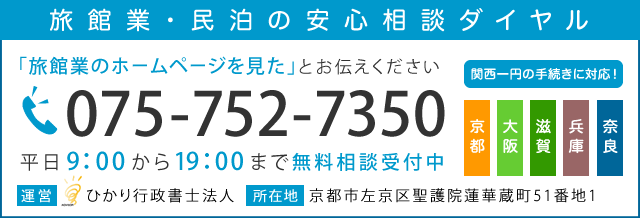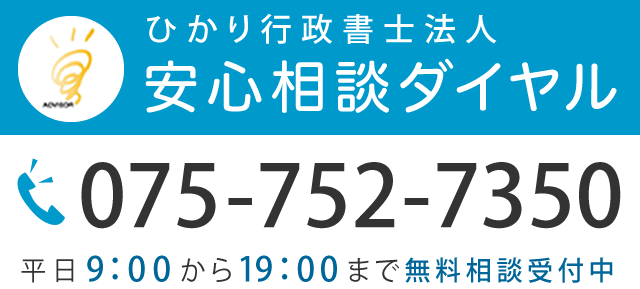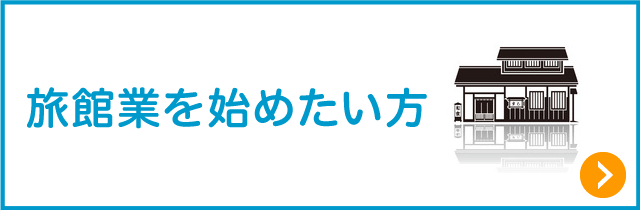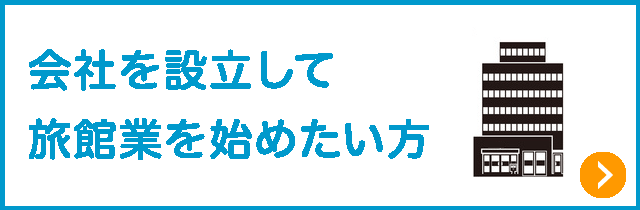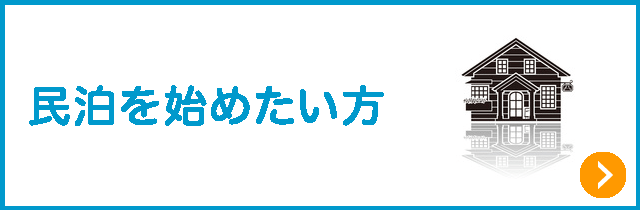ここでは、簡易宿所営業の許可申請について、詳しく解説していきたいと思います。
まずは次の用語について、定義を覚えておきましょう。
| 旅館・ホテル営業 |
- 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
|
| 簡易宿所営業 |
- 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
|
| 客 室 |
- 睡眠、休憩等宿泊者が利用し得る場所(客室に付属する浴室、便所、洗面所、板場、踏込み等であって、床の間、押入れ、共用の廊下及びこれに類する場所を除く。)
|
| 寝 室 |
- 客室内であって、浴室、便所その他睡眠又は休憩の場所に適さない場所を除いた場所
|
| 管 理 者 |
- 住民等からの苦情・問合せ及び緊急の事態に適切かつ迅速に対応するための体制における責任者をいう。
|
| 使用人 |
|
| 小規模宿泊施設 |
- 簡易宿所営業を営む施設で、次の要件を備えているもの
・施設が存する建築物が、①一戸建て又は長屋建て、②階数が3以下、③宿泊者と当該宿泊者以外の者の共用に供する部分が存しない構造であること。
・客室の数が1であること。
・施設のすべてを宿泊者の利用に供するもの。
・1回の宿泊について、宿泊者が9人以下で構成される1組に限られること。
|
簡易宿所営業の設備基準
| 他の営業の用途との区画 |
- 建築物内で、旅館業施設を、他の営業用途の施設及び住戸と明確に区画すること。
- 宿泊者と当該住戸の居住者が共用する部分がない構造とすること。
|
| 客室数 |
- 2人以上を収容する客室の数が客室の総数の2分の1を超えていること。
|
| 構造 |
- 窓を除き、客室と他の客室及び客室以外の施設との境は、壁又は板戸、ふすまその他これらに類するもの(固定されたものに限る。)で区画されていること。
- 窓は、鍵を掛けることができること。
- 客室の外部から内部の見通しを遮ることができる設備を設けること。
|
| 床面積 |
- 33m2以上
※ただし、宿泊者の数を10人未満とする場合は、3.3m2に当該
|
| 定員 |
- 寝 台 使 用:寝室3.0 m2以上/人
- 和式寝具使用:寝室2.5 m2以上/人
- 階層式寝台使用:寝室2.25m2以上/人
|
| 窓その他の開口部 |
|
| 換気設備等 |
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
|
施設の基準と管理体制
簡易宿所営業を行うためには、施設についての設備基準と人員の管理体制を整える必要があります。
また、施設内に玄関帳場を設ける同課でも設備基準・管理体制が変わってきますので、注意が必要です。
玄関帳場を設ける場合
| 設備基準 |
- 客室利用者が必ず通過し、出入りを視認できる場所に玄関帳場を設置すること。
- 玄関帳場には、受付に支障がない高さの受付台を設けること。
- 施設内に使用人等が使用できる便所等を設けるよう努めること。
|
| 管理体制 |
- 営業者又は使用人等は、人を宿泊させる間、施設内部に駐在すること。
- 営業者は、施設内部で面接の方法により、宿泊者の本人確認、人数確認及び鍵の受渡しをすること
|
施設外玄関帳場を設ける場合
| 設備基準 |
- 宿泊施設
①施設の出入口に鍵を設置
②電話機等を設置
③施設への人の出入状況を確認できる設備を設置
- 施設外玄関帳場
④宿泊施設まで10分以内に到着できる場所(道のりでおおむね 800m以内)に設けること。
⑤他の営業の用途、住戸と区画
⑥個人情報の取扱いに注意
⑦③による確認を常時行う。
⑧施設外玄関帳場の標示
- 使用人等の駐在場所
⑨宿泊施設まで10分以内に到着できる場所(道のりでおおむね 800m以内)であること。
⑩特別な構造設備は必要ないが、長時間の駐在が可能であること。
|
| 管理体制 |
- 営業者は、施設外玄関帳場内で面接の方法により、宿泊者の本人確認、人数確認及び鍵の受渡しをすること。
- 営業者又は使用人等は、人を宿泊させる間、施設外玄関帳場に駐在し、人の出入を常時確認すること。
- 営業者又は使用人等は、人を宿泊させる間、宿泊施設に10分以内に到着できる場所(道のりでおおむね800m以内)に駐在すること。
- 緊急対応を担当する使用人等が管理できる施設数は、1人当たり5施設までとする。
- 緊急対応を担当する使用人等が施設外玄関帳場に駐在する場合は、宿泊者の出入り確認等を行う別の担当者1名を駐在させること。
|
京町家を活用する場合
| 設備基準 |
- 宿泊施設
①施設への人の出入りの状況を確認することができる措置を講じること。
- 使用人等の駐在場所
②宿泊施設まで10分以内に到着できる場所(道のりでおおむね 800m以内)であること。
③長時間の駐在が可能であること。
|
| 管理体制 |
- 営業者は、施設内で面接の方法により、宿泊者の本人確認、人数確認及び鍵の受渡しをすること。
- 営業者又は使用人等は、人を宿泊させる間、宿泊施設に10分以内に到着できる場所(道のりでおおむね800m以内)に駐在すること。
- 緊急対応を担当する使用人等が管理できる施設数は、1人当たり5施設までとする。
|
簡易宿所営業許可申請の流れと注意点
旅館業許可を取得できる可能性があるかどうかを事前に調査しておく必要があります。
主に以下の点について、調査を行います。
1 建築基準法上の違反がないかどうか?
建築基準法に違反するような増改築を行っていないかどうか、建蔽率や採光が基準以上であるかどうかを調査する必要があります。
新築工事や増改築工事が必要な場合は、事前に京都市との協議の上で、主に以下の要件を満たすように施工を行います。
- 客室合計面積が33㎡以上
- 採光面積は床面積の1/8以上とること
- WC2箇所、浴槽付浴室1個以上(主要人員10名以下の場合)
- 玄関帳場のカウンターは2m以上とる事
2 都市計画法上の用途制限に合致しているかどうか?
物件の所在地によっては、旅館を営業すること自体ができない地域もあります。
営業することができない地域は以下の地域となります。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 第一種住居地域(3,000㎡超えの施設のみ不可)
3 施設が200㎡未満であるかどうか?
200㎡以上の施設で旅館業許可申請を行う場合は、建築確認(用途変更)が必要となり、用途の目的を「旅館」などに変更する必要でてきます。
この用途変更の手続きは主に建築士などが行いますが、費用も高く(通常100万円以上かかることも多いです。)、検査済証等の各種資料も必要となりますので、古い物件などでは用途変更自体が不可能な場合も多々あります。
4 消防署
必要な機器(消火器、防炎カーテン、絨毯等)や注意事項に関して、管轄消防署に事前の相談を行い、消防法令適合通知書の取得が必要となります。
5 学校照会
施設の近隣110m以内に学校や老人福祉施設、病床のある病院施設などが存在する場合は、本申請の前に学校照会という手続きが必要となります。
6 京都市の条例に基づく手続き
- 標識の設置・標識の設置状況の報告
- 近隣住民に説明
- 許可申請の際に行う報告・書類の作成
7 旅館業許可申請(本申請)
本申請の後、書類審査と並行して実地調査などが行われ、問題がなければ「営業許可証」が発行されます。
旅館業許可申請・住宅宿泊事業届出についてのお問合わせ
ひかり行政書士法人では、旅館業・住宅宿泊事業についてのご相談や申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
旅館業許可・住宅宿泊事業届出についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。
その他の許認可申請について

その他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。